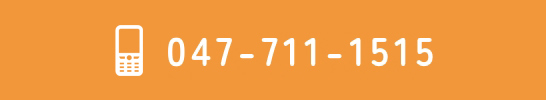内視鏡検査ってどんなことするの? 浦安の内視鏡検査なら
内視鏡検査で「何を見る」のか?
内視鏡の先端には、非常に高性能な小型カメラとライトが搭載されています。このカメラを通して、医師は消化管の粘膜表面をモニターで拡大して観察します。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の場合
内視鏡は、食道、胃、十二指腸の粘膜を観察します。
- 食道:
食道の壁の色や表面の滑らかさ、血管の状態、炎症の有無、潰瘍やポリープ、がんの兆候などを確認します。特に逆流性食道炎による炎症や、食道静脈瘤なども観察対象です。 - 胃
胃全体をくまなく観察します。胃の粘膜の色、胃壁の厚さ、ヒダの様子、粘液の状態、そして胃炎、胃潰瘍、胃ポリープ、胃がんなどの病変がないかを詳しく見ていきます。胃の動きや、食べたものの残り具合なども確認することがあります。病理検査が必要な場合には、粘膜の一部を採取して検査することもあります。 - 十二指腸
胃の出口に続く十二指腸の最初の部分(球部、下行部)の粘膜の状態を観察します。十二指腸潰瘍や炎症、ポリープなどがないかを確認します。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の場合
内視鏡は、大腸全体(直腸、S状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、盲腸)、そして多くの場合、小腸の一部(回盲部、回腸末端)の粘膜を観察します。
- 大腸全体
大腸のひだの様子、粘膜の色調、血管の走行、炎症の有無、潰瘍、憩室(けいしつ:大腸の壁にできる小さな袋状のくぼみ)、そして最も重要なポリープやがんがないかを徹底的に確認します。特にポリープは、将来がん化する可能性があるため、その大きさや形状、表面の様子などを詳細に観察し、必要に応じてその場で切除します。 - 回盲部・回腸末端:
大腸の最も奥にある盲腸と、小腸の終わり部分である回腸末端の観察も非常に重要です。クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患の診断にも役立ちます。
検査中の「処置」
内視鏡検査は、観察だけにとどまらず、その場で様々な処置を行うことができます。
- 生検(組織採取):
異常が疑われる病変が見つかった場合、内視鏡の先端から小さな鉗子(かんし)を出し、ごくわずかな組織を採取します。採取した組織は病理検査に回され、顕微鏡で詳しく調べることで、病変が良性か悪性か、炎症の種類などを確定診断します。痛みはほとんどありません。 - ポリープ切除
大腸カメラの場合、がんになる可能性のあるポリープが見つかれば、その場で切除することが可能です。これにより、将来的な大腸がんの発生リスクを低減することができます。切除方法には、スネアというワイヤーをポリープの根元にかけて切除する方法が一般的です。 - 止血処置
出血している部位が見つかった場合、クリップや薬剤の散布などを用いて止血処置を行うことがあります。 - 異物除去
誤って飲み込んでしまった食べ物や、その他の異物を取り除くことも可能です。
浦安市で内視鏡検査なら、いちょうの森クリニック 浦安へ
内視鏡検査は、単に消化管を「覗き見る」だけでなく、その詳細な変化を捉え、診断から治療までをその場で行える非常に精密な検査です。
検査に不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、浦安市にあるいちょうの森クリニックでは、鎮静剤を使用した内視鏡検査を提供しており、専門医が担当いたしますので、安心して検査を受けていただけます。
もし消化器に関する気になる症状がございましたら、ぜひ一度当院にご相談ください。